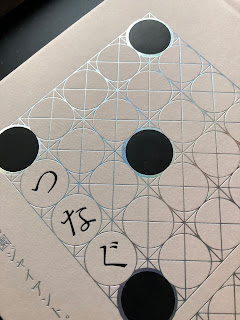あをぐみがデザインを担当した絵本『いま、日本は戦争をしている −太平洋戦争のときの子どもたち−』(小峰書店)をご紹介します。
絵と文は、堀川理万子さん。
かがくのとも(福音館書店)の『さんかくで いえを つくろう』や『そっちから わたし、どんなふうに みえている?』に続き、堀川さんの本のデザインを担当するのは3冊目となりました。
「戦争」というテーマに向き合うことは、個人的に「人生の宿題」のような気がしていたので、ここで大きなチャンスをいただけたことに、運命的なものを感じています。
デザインに取り掛かる前に、äも取材に同行して体験談を直に聞くことができました。
インタビューだけでも大仕事なのですが、堀川さんは同時にイラストのラフと、そこに添える文章さえも平行して書いていくのです。しかもそれを数日くりかえして精度をあげていく……そのスピードと集中力には驚愕しました。
取材を終えてから、それらをもとに本格的にイラストを仕上げていくのですが、ある程度仕上がった段階で取材先に確認し、修正をくりかえす。
これは相当な覚悟とエネルギーが必要だった思います。
完成したイラストには、写真とはまた違った趣きが添えられ、戦時下でのほんとうの日常が封じ込められているように僕には見えました。
たったひとりの方への取材でもたいへんなのに、17人の方と向き合った。
結果、完成した本もおのずと大作になっています。
子どもたちはもちろん、すべての人に読んでもらいたい、と強く感じています。
原画展も開催されるので、リンク先からスケジュールを確認いただき、ぜひ足をお運びください。本の外側が感じられる貴重な機会です。(ä)